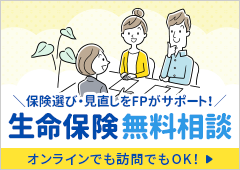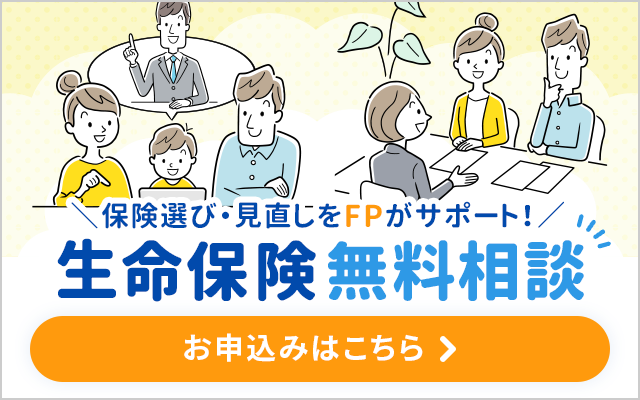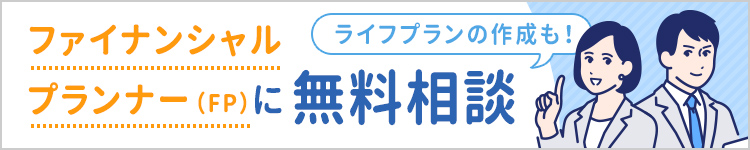変額保険が向いている人とは?メリット・デメリットを解説
更新日:
変額保険は、死亡保障を準備しながら資産形成が期待できる保険です。
「変額」と名がついているとおり受け取れる「額」が「変わる」ため、想定よりも受け取れる額が少なくなる可能性があることから心配の声もお聞きします。
変額保険は元本割れ等のリスクがある一方で、受け取れる額が元本よりも大きくなり資産を作ることができる可能性がある保険です。検討する際には、ご自身が「変額保険が向いている人」に当てはまるかどうかをチェックすることが大切です。
では変額保険が向いている人とはどんな人なのでしょうか?
この記事では、変額保険の基本的な仕組み、向いている人、メリット・デメリットまで解説いたします。
変額保険とは?基本的な仕組みの解説
変額保険の基本的な特徴
保険料の一部が運用されるため受取額が増える可能性がある
変額保険とは、生命保険の一種でありながら、投資信託のような運用機能を備えた保険商品です。
その最大の特徴は、保険契約者が支払った保険料の一部が、株式や債券などを対象とする投資信託を利用して運用されることです。
運用成果によって、死亡保険金や解約返戻金、満期保険金が変動するため、運用が成功すれば受取額が増加する可能性があります。
元本割れのリスクがある
一方で、市場の状況によっては元本割れのリスクも伴います。ただし、契約時に定めた基本保険金額は最低保証され、運用が不調でも下回ることはありません。
変額保険で受け取れるお金
変額保険は、死亡保険金や満期保険金、解約返戻金が市場の動向によって変動します。
万が一の死亡時に受け取ることができる死亡保険金は、契約時にあらかじめ定めてある基本保険金額を下回ることはありません。
一方で、満期を迎えたときに受け取ることができる満期保険金や変額保険を解約したときに受け取ることができる解約返戻金は、その時点までに払い込んである保険料の累計額よりも下回る可能性があります。
| 受け取れる お金 |
受け取れる タイミング |
受け取れる額の変動 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 亡くなったとき | 変動あり 契約時に定めた基本保険金額を下回ることはない |
| 満期保険金 | 満期を迎えたとき(生存時) | 変動あり 既払込保険料累計額を下回ることがある |
| 解約返戻金 | 途中で解約したとき(生存時) | 変動あり 既払込保険料累計額を下回ることがある |
変額保険と定額保険の違い
変額保険は、株式や債券などの運用実績に応じて保険金額や解約返戻金が変動するため、比較的ハイリスクハイリターンと言えるでしょう。
リスクを避け安定した保障を最優先したいという方であれば、市場の影響を受けにくい定額保険が適しています。
また、保険は一般的にインフレに弱いと言われています。インフレで物価が上がり、お金の価値が下がっても、定額保険であれば受け取る保険金額は最初に決まっているため、実際の価値が減ってしまいます。
一方、変額保険は、インフレに合わせて保障額が増えることが多いため(運用の結果によるため注意が必要です)、インフレによって資産が減るのを防ぎやすくなります。
主な違いのまとめ
| 項目 | 変額保険 | 定額保険 |
|---|---|---|
| 保険金額 | 運用実績に応じて変動 | 一定 |
| 解約返戻金 | 運用実績に応じて変動 | 一定 |
| リスク | 高い (リターンも期待できる) |
低い |
| 運用先 | 株式や債券など市場投資 | 固定利率での運用 |
| 向いている人 | リスクを取って リターンを狙いたい人 |
安定した保障を求める人 |
| インフレの影響 | 受けにくい | 受ける |
変額保険と投資信託どっちを選ぶべき?
万が一の死亡保障と資産運用を両立したい人には変額保険が向いています。
一方で、保険の機能は必要なく資産形成のみを目的とする人には投資信託が適しています。
さまざまな項目において違いがあるため、確認しておきましょう。
主な違いの比較表
| 項目 | 変額保険 | 投資信託 |
|---|---|---|
| 目的 | 保険(保障)+ 資産運用 |
純粋な資産運用 |
| 保障機能 | 死亡保障などあり | なし |
| 運用先の 選択肢 |
保険会社が選定した ファンドに限定 |
自由に選択可能 |
| コスト | 保険料+ 運用手数料がかかる |
信託報酬や 購入手数料がかかる |
| 流動性 | 解約手数料が かかる期間がある |
自由に解約可能 |
| 税制優遇 | 相続税・贈与税で 優遇がある場合あり |
NISA口座で投資することで 税制優遇の利用が可能 |
変額保険の商品をまとめて資料請求
変額保険、加入したほうがいい?
FPに相談してみましょう!
変額保険のメリット
変額保険のメリットは次のようなことが挙げられます。
- 保障がつく
- 税制上の優遇措置
- 認知症時にも引き出せる
メリット①生命保険のため保障がつく
変額保険の大きなメリットの一つは、保障機能が備わっている点です。
生命保険としての基本的な役割を果たしながら、投資運用も並行して行うことができるため、万が一の事態に備えつつ資産を増やす可能性も追求できます。
死亡保障が設定されている
一般的に変額保険には死亡保障が設定されており、被保険者が亡くなった際には契約時に定めた死亡保険金が支払われます。このため、家族や遺族に対する経済的な支えを確保することができるのです。
複数の特約が用意されていることも
また、死亡保障だけではなく、三大疾病や介護などの保障もつけることができるものもあります。他にも三大疾病や特定八疾病で一定の条件を満たすとその後の保険料を契約者が払うことなく資産形成を続けることができる特約も存在します。
運用成績にかかわらず最低限の保障が確保される
さらに、契約時に設定した最低保証額(基本保険金額)があるため、運用成績が振るわない場合でも最低限の保障が維持されることから安心感を得ることができます。ただし、保障の内容や金額は契約内容によって異なるため、加入前にしっかりと確認することが重要です。
メリット②税制上の優遇措置
変額保険では税制上の優遇措置が適用される点が大きなメリットになります。
保険料が控除の対象になる
まず、変額保険の保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税および住民税の負担を軽減することが可能です。
生命保険料控除を利用することで、最大で年間4万円(所得税)および2.8万円(住民税)の控除を受けることができるため、所得税の課税所得を一定額減らすことができます。これにより、毎年の税金負担を軽減できる可能性があるため、特に所得が高い方にとっては税金の軽減効果が期待できます。
死亡保険金(500万円以内)にかかる相続税が非課税となる
さらに、変額保険の契約者が死亡した場合、受取人に支払われる死亡保険金にも相続税の非課税枠が適用されます。法定相続人一人当たり500万円の非課税枠が設けられており、相続税の対象となる資産を減少させることが可能です。これにより、受取人が相続税を支払う際の負担を軽くすることができ、遺産を効率的に遺族に引き継ぐことができます。
ただし、税制の適用範囲や控除額は、法律や政策の変更に伴い変わることがあります。個別の税務などについての詳細は、所轄の税務署などに必ずご確認ください。
メリット③認知症時には本人以外が引き出せる
変額保険の特徴として、指定代理請求人制度が設けられていることが挙げられます。
この制度では、契約者が認知症や高度障害などにより判断能力を失った場合でも、事前に指定した代理請求人が解約や保険金の請求を行うことができます。契約者本人が手続きできなくなった場合でも、資金をスムーズに引き出せる仕組みが確保されているのです。
一方で、NISAや一般的な金融商品では、契約者が認知症などで判断能力を喪失した場合には成年後見人の選任が必要になるため、資金を引き出すまでに時間や手間、費用がかかることが多いです。
また、希望通りの用途に活用できないこともあります。
変額保険では、万が一に備えて指定代理請求人を設定しておくことで、認知症のリスクにも対応可能です。この点で、柔軟性と実用性を兼ね備えた商品と言えます。
変額保険のデメリット
変額保険のデメリットは次のようなことが挙げられます。
- 運用リスクと元本割れの可能性
- 保障と運用それぞれに手数料がかかる
- 解約で手数料が発生する
デメリット①運用リスクと元本割れの可能性
変額保険には、運用リスクと元本割れの可能性が伴います。これは、この保険が投資信託などの金融商品と連動しているためです。
市場の動向に応じて保険の価値が変動するため、経済状況が悪化した場合には元本割れのリスクが存在します。特に、株式市場や債券市場の変動が大きいときには、その影響を大きく受けることがあります。
解約返戻金や満期保険金は元本保証がないため、契約時に支払った保険料以上の価値を得られない可能性がある点に注意が必要です。
また、長期的に運用を行うことになるため、短期的な市場の変動に一喜一憂することなく冷静に対応する心構えが求められます。投資経験が少ない方にとっては、リスクの理解が難しいことがデメリットとなるかもしれません。
デメリット②保障と運用それぞれに手数料がかかる
変額保険は、保障と資産運用の両方を兼ね備えた金融商品であるため、それぞれに手数料が発生する点に注意が必要です。
保障部分
まず、保障部分に関する手数料(保険料)は、死亡保険や特定のリスクに備えるための費用として徴収されます。保険会社が提供する保障内容によって手数料は異なり、年齢や健康状態に応じて変動することがあります。
資産運用部分
次に、資産運用部分については、投資信託や株式市場での運用サービスを提供するための手数料がかかります。これには、運用管理費や信託報酬が含まれ、運用成績にかかわらず固定的に発生することが一般的です。
このように、変額保険の手数料は保障と運用の双方にわたって発生することがデメリットともいえるでしょう。契約者はそのコストを理解した上で契約することが求められます。
デメリット③解約時に保険会社に払う手数料が発生する
変額保険は途中解約ができますが、注意点があります。それは、10年未満で解約や減額を行う場合、一般的に解約控除と呼ばれる手数料が発生することです。
よって、解約タイミングによっては、解約返戻金が想定よりも少なくなることがあります。
この仕組みは一見デメリットに思えますが、逆に契約を続ける心理的なハードルとして働く点が特徴的です。
「途中で解約すると損をする」という契約者の意識が、長期継続を後押しします。資産運用は短期では成果が見えにくく、時間をかけることで運用益が期待できるため、この「辞めにくさ」は長期的な資産形成において大きなメリットとなるのです。
10年以上継続すれば解約控除がなくなり、運用成果を活かした解約返戻金を受け取ることが可能です。
変額保険は、短期的な解約を防ぎつつ、長期契約の魅力を引き出す仕組みが備わっています。「長く続けたいけれど、なかなか決心がつかない」という方にとって、一見するとデメリットに見える解約控除が背中を押してくれる存在になるかもしれません。
変額保険の商品をまとめて資料請求
変額保険、加入したほうがいい?
FPに相談してみましょう!
変額保険が向いている人の特徴
- 保険と投資を別々に管理するのが苦手
- 遺すことも考慮して資産形成したい
- 守りの運用をしたい
向いている人①保険と投資を別々に管理するのが苦手な人
変額保険は保険と投資を一体化した金融商品です。これら2つを別々に管理することを煩雑に感じる人にとって、変額保険は効率的な選択肢となります。
一つの商品で保険と投資を管理できる
保険と投資は一般的に異なる目的を持ち、それぞれのリスクや運用方法を理解し管理する必要があります。しかし、変額保険は保険としての保障を維持しつつ投資の要素も組み込まれているため、一つの商品で両方を管理できる利便性があります。
このため、保険と投資を個別に選び、定期的に見直す手間を省きたいと考える人は「変額保険が向いている人」といえるでしょう。
投資経験が浅い方や不安がある方でも比較的安心
また、変額保険は保険会社が提供するプロフェッショナルな運用サービスを利用できるため、投資経験が浅い方や、投資のタイミングや商品選びに不安がある方でも比較的安心して利用することができます。
さらに、専門的な知識が必要な資産運用を保険会社に任せることができるため、時間や労力を削減することが可能です。ただし、運用成果によっては元本割れのリスクもあるため、商品選びの際にはその特性を十分に理解し、ご自身がどの程度のリスクを許容できるか検討することが重要です。
このように、変額保険は保険と投資を一つの商品でスマートに管理したいと考える人にとって、非常に魅力的な選択肢となります。特に、仕事や家庭が忙しく時間的を余裕がない方や、細かい資産運用の管理に自信がない方には、保険と投資を一度にまとめて管理できる点が大きなメリットになるかもしれません。
向いている人②遺すことも考慮して資産形成したい人
資産形成を考える上で、自分自身のためだけでなく遺族や次世代のために資産を遺したいと考える人も「変額保険が向いている人」といえるでしょう。
遺族のための資産を準備しつつ運用次第で増やせる
変額保険は、保障機能と投資機能を兼ね備えており、運用次第で資産を増やすことが可能です。特に、将来のインフレリスクを考慮に入れると、変額保険は資産の実質的な価値を維持または増加させる可能性があります。通常の貯蓄ではカバーしきれないインフレの影響を緩和しつつ、遺族に一定額以上の資産を遺すことができる点が大きなメリットといえます。
税負担の軽減ができることも
また、変額保険を利用することで税制上の優遇措置を受けられます。これにより、遺族が負担する相続税を軽減できることがあります。
資産を遺すことを考慮している人にとって、こうした多角的なメリットを享受できる変額保険は、資産形成を考えるうえで有力な選択肢となるでしょう。
向いている人③守りの運用をしたい人
変額保険はリスクを伴う運用をしながらも資産を守りたいと考える人に向いています。
投資の世界ではリスクを完全に排除することは難しいですが、変額保険を活用することである程度の保障を確保しつつ投資を行うことができます。言い換えると、資産の一部を市場の変動にさらしつつも、保障という安全網を持つことでリスクに対する不安を軽減し、安定した運用を目指すことが可能となります。
万が一の保障を確保しつつ資産運用ができる
守りの運用を重視する人は、資産の価値を大きく減少させることなく、長期的に資産を増やしていくことを重視することが多いでしょう。
変額保険は、死亡保障などの保険機能を有し、万が一の場合には家族に資産を遺すことができるため、リスク分散の一環として利用することができます。
また、商品によっては積立金を引き出すことができるものもあるため、急な資金需要にも柔軟に対応できます。
長寿リスクへの備えに繋がることも
認知症や介護といった長寿リスクへの備えを確保することもできます。
備えの一例としては、指定代理請求人制度によって、認知症になっても事前に指定した代理請求人が資金を引き出すこともできます。
また例えば、介護保障がある変額保険では、所定の条件(被保険者の介護費用に充てるため等)に該当すれば介護保険金を非課税で受け取ることができます。
「変額保険はやめたほうがいい・おすすめしない」と言われる理由とは?
変額保険はやめたほうがいいと言われる理由は、主に以下の点に集約されます。
元本割れリスクがある
まず、運用リスクが高いことが挙げられます。
変額保険は投資信託のように資産を運用するため、相場の変動によって元本割れのリスクが存在します。特に、投資の経験が浅い人やリスクを許容できない人にとっては、これが大きなデメリットとなり得ます。
手数料がかかる
次に、手数料の問題です。
変額保険は保障と運用それぞれに手数料がかかるため、これが長期的な資産形成において負担となることがあります。また、早期解約時にも手数料が発生するため、急な資金需要に対応しにくいという側面もあります。
保険と投資どちらの知識も必要
さらに、変額保険の仕組みや投資商品の選択が複雑であるため、十分な知識がないと適切な運用が難しくなる可能性があります。
保険と投資を一体化した商品であるため、どちらか一方に特化したい人には不向きであると考えられます。
長期的な運用が必要
最後に、市場のインフレ状況や経済の変動によって期待通りの利回りが得られない場合もあるため、長期的な視野での運用が求められます。リスク・デメリットを十分に理解できる人でないと、変額保険は望んだ結果を得るのが難しいかもしれません。
これらの理由から、変額保険はやめたほうがいい・おすすめしないとされる場合があります。
変額保険の商品をまとめて資料請求
変額保険、加入したほうがいい?
FPに相談してみましょう!
変額保険に加入する際の注意点
自分の加入目的に合っているか
変額保険に加入する際にまず考慮すべきは、自分の加入目的に合っているかどうかです。
変額保険は保険料の一部が投資信託などに運用され、その運用成果によって将来の受取金額が変動します。このため、資産を積極的に増やしたいと考えている人にとっては魅力的な選択肢となりますが、元本保証がないため、リスクを受け入れる覚悟が必要です。
加入目的を明確にすることは、変額保険の長所と短所を理解する上で重要です。
資産形成を重視するのか、それとも保障を重視するのか
資産形成を重視する場合は、運用リスクをしっかりと理解し、リスク許容度に応じた商品を選ぶことが求められます。
一方で保障を重視する場合には、変額保険が他の保険商品と比較してどのようなメリットがあるのかを確認し、必要な保障内容が含まれているかをしっかりと見極めることが重要です。
変額保険は保障と運用が一体となった商品であるため、目的に応じてどちらに重きを置くかを明確にし、それに合ったプランを選ぶことが求められます。
将来のお金まわりを想定する
さらに、ライフステージや将来的な資金ニーズを考慮することも重要です。例えば、子供の教育資金や老後の生活資金としての利用を考える場合、それに応じた運用期間やリスク許容度を設定する必要があります。
加入目的を明確にし、自分自身のライフプランに適した商品を選ぶことが、変額保険を活用する上での成功の鍵となります。
商品の比較ができているか
変額保険に加入する際には、複数の商品をしっかり比較することが重要です。
この比較を怠ると、自分のニーズに合わない商品を選んでしまうリスクが高まります。
保険会社ごとの違い
まず、保険会社ごとに提供されている変額保険の運用方針や保障内容を確認しましょう。
運用先の選択肢が多いほど、自分のリスク許容度や投資目標に合った商品を見つけやすくなります。また、各商品にかかる手数料の違いも見逃せません。手数料は運用成果に直接影響を与えるため、総合的なコストをしっかり把握することが必要です。
保障内容の違い
さらに、保障内容の違いにも注目しましょう。死亡保障や介護保障など生命保険としての基本的な保障がどの程度含まれているのかを確認し、万が一の場合に備えた適切な保障がある商品を選ぶことが重要です。
過去の運用実績
また、商品の比較を行う際には過去の運用実績も参考にしましょう。過去の実績が良いからといって、将来も同様の成果が得られるとは限りませんが、運用方針やリスク管理の質を判断するための一助となります。
自分に合う商品を見つける
最後に、比較する際は自分の資産形成の目標やライフステージを明確にしておくことが大切です。これにより、短期的な利益を追求するのか、長期的な資産形成を目指すのかといった、自分自身のプランに最も合った商品を選択することができるでしょう。商品比較を通じて、自分に最適な変額保険を選ぶことが、後悔しない保険選びの第一歩となります。
専門家への相談を活用する
変額保険は、投資信託を利用した運用を行うため、専門的な知識が求められる金融商品です。
そのため、加入を検討する際には、専門家の意見を活用することが非常に重要です。
ファイナンシャルプランナーや保険の専門家は、あなたの資産状況やライフプランに基づいて最適なアドバイスを提供してくれます。
特に、変額保険の運用リスクや手数料、税制上の優遇措置についての詳細な説明を受けることで、自分にとって本当に適した選択であるかを判断する助けとなります。
また、変額保険は市場の変動に影響を受けやすいため、長期的な視点での資産形成が求められます。
専門家は、これらのリスクをどのようにマネージするかについてもアドバイスを提供します。例えば、リスク許容度に応じた運用方針の設定や、適切なタイミングでのポートフォリオの見直しなど、専門的な視点からのサポートを受けることで、安心して資産運用を行うことができます。
専門家への相談は、契約後のフォローアップにも役立ちます。
市場の変動やライフイベントに応じて、必要に応じて保険内容を調整することができるため、長期にわたって安心して加入を続けることができます。
したがって、変額保険に加入する際には、専門家の知識を最大限に活用することが、成功する資産運用の鍵となります。
変額保険や資産形成のこと、ぜひご相談ください
今回取り上げた「変額保険」は、保険でありながら資産形成ができる商品です。
- 既に医療保険や死亡保険にも入っているのに変額保険も、となると家計の負担が心配
- iDeCo、NISA、変額保険…老後資金を準備する方法がたくさんあって違いがわからない
- 変額保険と投資信託どっちがいいの?
- 変額保険は保険料全額が運用されないから無駄なの?
- 資産運用はトラブルが不安…
といったお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
変額保険の商品をまとめて資料請求
変額保険、加入したほうがいい?
FPに相談してみましょう!
まとめ
変額保険は、保障と資産運用を一体化した金融商品であり、加入には慎重な検討が必要です。
本記事では、変額保険の基本的な特徴や定額保険との違い、並びに変額保険のメリットとデメリットについて詳しく解説しました。
変額保険のメリットとしては、保障がつくことや税制上の優遇措置、認知症時の引き出しが可能である点が挙げられます。一方で、運用リスクや元本割れの可能性、手数料の存在などのデメリットも存在します。こうしたメリットとデメリットを把握することで、変額保険が自分に適しているかどうかを判断する手助けになります。
さらに、変額保険が向いている人の特徴としては、保険と投資を別々に管理するのが苦手な人や、資産を遺すことを考慮している人、守りの運用を求める人が挙げられます。
これらの特徴を持つ方にとっては、変額保険が一つの選択肢となり得ますが、加入前には専門家への相談を活用することを強くおすすめします。専門家の視点からアドバイスを受けることで、自分に合った保険商品を選ぶことができ、将来的なリスクを軽減することが可能です。
変額保険に加入する際は個々のライフプランやリスク許容度をよく検討することが大切です。
自己判断が難しい場合は、信頼できる保険の専門家やファイナンシャルプランナーに相談し、納得のいく形で保険を選びましょう。
ぜひ、変額保険を資産形成や保障の確保にお役立ていただければと思います。
本記事の内容は一般的な説明であり、個別の契約条件やリスクについて保証するものではありません。
ご契約の際は、契約書やパンフレットをよく読み、ご自身の判断でお申し込みください。
不明点がある場合は、金融機関や専門家へご相談ください。
- 「変額保険」には、お客さまにご負担いただく諸費用およびリスクがあります
-
お客さまにご負担いただく諸費用について
主なものは以下のとおりです。
保険契約
関係費ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、新契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。 資産運用
関係費投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。 解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生いたします)。 - 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
- ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。
リスクについて
「変額保険」には商品の種類によって次のようなリスクがあります。
リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは、商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。変額保険 この保険は国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。
執筆者情報
執筆者
秋山 保
(CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、1種証券外務員/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「難しいことを、やさしく。やさしいことを、深く。」をモットーに、スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすく
ご説明させていただきます。
掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
自分に合った保険を探す!
保険料シミュレーション
複数の保険商品を
まとめて比較・お見積もりできます!

 0120-873-100
0120-873-100