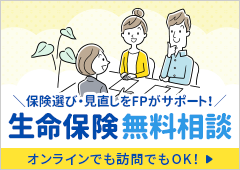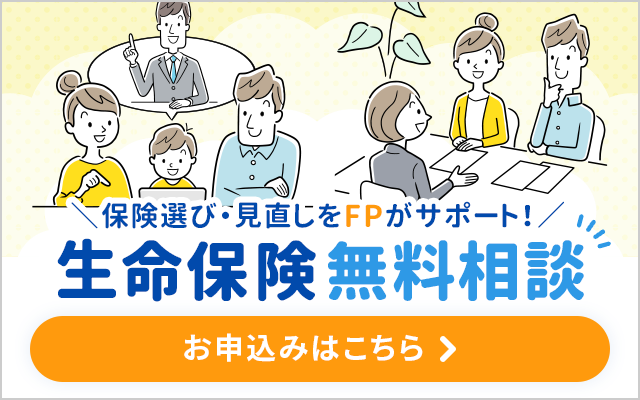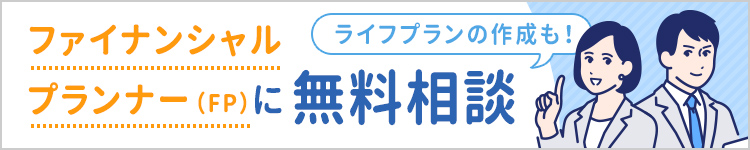死亡保険の選び方は?3つの基本型を解説
複雑で難しいイメージの死亡保険ですが、基本となるのは実は3種類。
この3種類にそれぞれ特約がついているので、各商品ごとに特徴が異なり、商品の種類が多く感じてしまうだけなのです。本当はそんなに複雑なものではありません。
全ての保険はこの3種類をベースに作られています。
まずは基本のカタチを理解し、あなたのタイプにあった死亡保険を選びましょう。
3種類の基本型
定期保険
定期保険の特徴
一定期間の死亡保障を目的とした、掛け捨てで保険料が割安な保険
「定期保険」は保険期間があらかじめ決められた死亡保険です。保険期間内に死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金の支払いがあります。
満期になった場合、満期保険金はありません。
また、途中解約をした場合には、解約返戻金が全くない商品と解約返戻金がある商品があります。
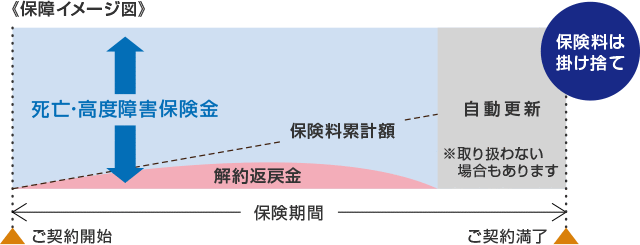
ポイント
- 10年/20年など、ライフプランに合わせて必要な保険期間を選べる
- 毎月の保険料が安いので、高額な保障を選びやすい
- 保険期間が過ぎると保障が終わる
- 更新後に保険料が上がる
- 保険料は掛け捨て
定期保険の上手な活用法
定期保険は10年/20年など、保険期間が選べるのが利点です。
必要な一定期間のみ加入することができ、掛け捨てのため保険料は安く、1,000万円、2,000万円など大きな保障を備えられるところが魅力です。
例えば子どものいるご家庭で、子どもが自立するまでの期間に限定して保障を持つことで、保険料で家計を圧迫することなく、大きな保障を持つことができます。
ただし、保険期間満了後には保障がなくなってしまい、更新する場合は更新時の年齢によって保険料が決定するので、更新するごとに支払う保険料は高くなってしまいます。
ずっと必要になる保障は終身保険で準備し、状況に応じた不足分を定期保険で補うなど「一定期間だけ保障が必要」という場合の活用方法として検討することをおすすめします。
なお、定期保険にはいろいろな応用パターンがありますので、あわせてご紹介します。
長期定期保険(長期平準定期保険)
長期定期保険は、保険期間中一定の保険金額が保障される定期保険です。
保障期間の途中で解約返戻金がピークとなり、満期時にはなくなる仕組みになっています。
逓減(ていげん)定期保険
逓減定期保険は、契約時の保険金額から年々保障額が減少していく定期保険です。
保険金の受け取りは一括となり、収入保障保険とは受け取り方法が異なります。
最初は大きな保障が必要だが、だんだん必要額が減っていく場合に活用すると良いでしょう。
収入保障保険
収入保障保険は、契約者に万が一のことがあった場合、遺された家族に対して毎月10万円や15万円が年金のように支払われる保険です。保険期間も60歳や65歳など、家族構成に合わせて設定することが可能です。
また、商品によっては一括で受け取れるものもありますが、受取総額は若干少なくなります。
契約時が死亡保険金総額のピークとなり、年数が経つごとに支払総額が減少する仕組みです。
子供の成長にしたがい、必要保障額は減っていきます。収入保障保険は必要保障額と死亡保険金額の総額が連動した合理的な保険と言え、一定期間大きな保障額を持つよりも保険料を安く備えることができます。
逓増(ていぞう)定期保険
逓増定期保険は、契約時の保険金額から年々保障額が増加していく定期保険です。
時間の経過とともに必要保障額が増える場合に適しています。保障期間の途中で解約返戻金がピークとなり、満期時にはなくなる仕組みです。
特に法人が活用することが多い保険です。
終身保険
終身保険の特徴
一生涯の死亡保障を目的とし、解約返戻金があり、保険料払込終了後も解約返戻金が増加していく保険
「終身保険」は保険期間が予め決められた死亡保険です。保険期間内に死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金の支払いがあります。
満期になった場合、満期保険金はありません。
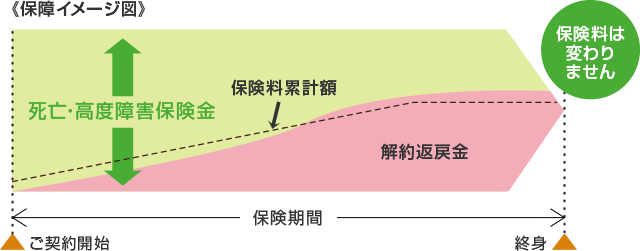
図は一般的な商品イメージです。契約されたときの年齢、保険料の払込期間等によって異なります。
ポイント
- 保障が一生涯続き、いつ亡くなっても死亡保険金が受け取れる
- 保険料が変わらない
- 解約返戻金があるので掛け捨てじゃない
- 毎月の保険料が高い
- 途中解約すると損をしてしまうこともある
終身保険の上手な活用法
終身保険は保障が一生涯続くため、解約せずに継続すれば必ず保険金を残せます。
さらに、貯蓄の機能(解約返戻金)もあることから、『保障+貯蓄』の両方を求める方には特におすすめです。
また、契約時の年齢で決まった保険料は一生涯変わらず、保険金を受け取ることができます。更新で保険料が上がらないという安心感は大きな強みです。
お葬式代や相続税対策など、「将来必ず必要になる保障」の準備として検討すると良いでしょう。
一部の終身保険では、一定の払込期間を過ぎると解約返戻金が払込保険料の総額を上回る商品もあります。
このように貯蓄性が高い終身保険もあり、死亡保障を持ちながら「子どもの学費」や「老後資金」に活用する方法も一般的となっています。
ただし、払込期間中に途中で解約してしまうと元本割れのリスクがあります。
結果的に損をしないためにも、保険金額をある程度抑えつつ、無理なく計画的に利用することが大切です。
養老保険
養老保険の特徴
一定期間の死亡保障と、契約満期時には死亡保障と同額の満期保険金が受け取れる保険
「養老保険」は、保険期間があらかじめ決められ、満期時には満期保険金を受け取ることができる貯蓄型の死亡保険です。
満期までの「死亡保険金」と満期時に受け取る「満期保険金」は同じ金額で、生きていても亡くなっても受け取ることができます。途中解約をした時は、解約返戻金があります。
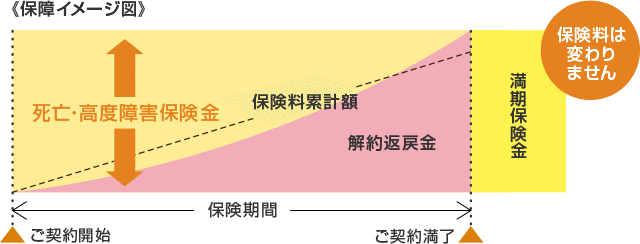
ポイント
- 貯蓄性がある
- 満期時には死亡保障と同額の満期金を受け取ることができる
- 保障期間が過ぎると保障が終わる
- 積立型の保険商品なので保険料が高い
養老保険の上手な活用法
養老保険は、10年や20年など保険期間があらかじめ決められ、死亡保障と貯蓄を兼ね備えた保険です。
保障期間中に死亡した場合は死亡保険金が、保険期間満了時まで生存していた場合は死亡保険金と同額の満期金が受け取れます。
最後まで契約を継続することで確実にお金を貯めることができる、積立貯蓄に死亡保障がついたような仕組みになっています。
ただし、満期金として受け取る分も保険料に含まれるため、掛け捨ての定期保険に比べて保険料は割高です。
利率が高い時代は、払った保険料以上の満期保険金を受け取れる商品が主流でした。しかし、利率が低い時代の商品は必ずしもそうではありません。
終身保険と同様、積み立ての要素がある商品は、具体的な試算をした後に加入を検討することが大切です。
死亡保険の目的別の選び方
ご紹介してきた特徴や保障の活用法を一覧にまとめました。
あくまで大枠の説明ですが、これらをもとに仕組みを理解することで、ご自身にあった商品を選びやすくなるかと思います。
| 定期保険 | 終身保険 | 養老保険 | |
|---|---|---|---|
| 保障期間 | 一定期間のみ | 一生涯 | 一定期間のみ |
| 保険料 | 安い/掛け捨て | 高い | 高い |
| 目的別の 活用法 |
一定期間の保障の増額 |
|
死亡保障を兼ねた積み立て |
|
<保障> <積み立て> |
<保障> <積み立て> |
<積み立て> |
|
| 解約返戻金 | なし | あり | あり |
監修者情報
監修者
秋山 保
(CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、1種証券外務員/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「難しいことを、やさしく。やさしいことを、深く。」をモットーに、スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすく
ご説明させていただきます。
掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
死亡保険の基本情報
死亡保険の基礎知識
自分に合った保険を探す!
保険料シミュレーション
複数の保険商品を
まとめて比較・お見積もりできます!

 0120-873-100
0120-873-100