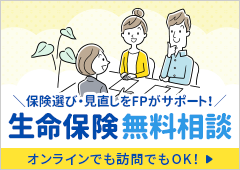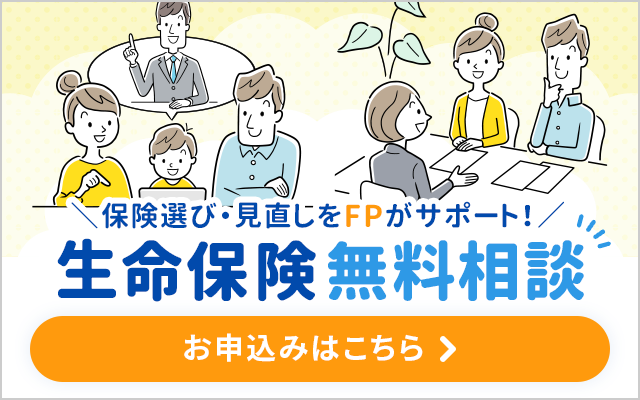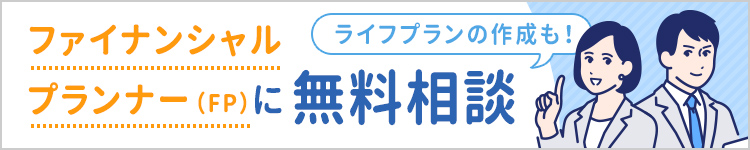生命保険の申込の告知で嘘をついたらどうなる?
更新日:
生命保険に加入する際には、被保険者の健康状態や病歴を保険会社に正確に伝える「告知義務」があります。
告知内容によっては加入できないこともあるため、持病があっても隠そうと考える方もいるかもしれません。
しかし、それは「告知義務違反」にあたり、発覚すれば保険料を支払っていても保険金が受け取れない可能性があります。
一時的に加入できても、いざという時に保障が受けられなくては意味がありません。
この記事では、告知義務とは何か、違反すると具体的にどうなるのか、詳しく解説していきます。
告知義務とは?
生命保険に加入する際、被保険者や契約者は、保険会社から求められた病歴や健康状態などの「重要事項のうち、告知を求める事項」について、正確に伝える必要があります。
これを「告知義務」といいます。
告知義務を負う人
告知義務は、「被保険者(保障の対象となる方)」および「契約者(契約を申し込む方)」が負います。
告知の方法
告知は各保険会社が定めた方法で行います。主な方法は以下のとおりです。
告知書への記入
被保険者が保険会社の定めた告知書(告知欄)に必要事項を記入し、提出します。
健康診断書や人間ドックの結果のコピー提出
被保険者が告知書に記入し、勤務先などで受けた健康診断書を添付して提出します。
この場合、新たな医師の診断は必要ありません。
保険会社指定病院等での診査
医師が告知書をもとに質問を行い、被保険者がそれに回答します。
告知書への記入は被保険者本人が行い、医師は診査結果を別途記録します。被保険者は自身が記入した告知書を確認のうえ、署名します。
告知はなぜ必要?
生命保険は、相互扶助の仕組みで成り立っています。
多くの人が少しずつ「保険料」を出し合い、万一の際にはそのお金から「保険金」を支払うという、助け合いの精神で作られた仕組みです。この仕組みによって、一人ひとりが負担する保険料は少なく、でも万一の際には集まったお金で備えられます。
この助け合いの仕組みを公平に維持するためには、契約者それぞれのリスクをできるだけ同じレベルに保つことが必要です。
そこで設けられているのが「告知義務」です。
生命保険に加入する際には、保険会社から求められた健康状態や病歴などを、ありのまま正確に伝えなければなりません。
保険会社は、この告知内容をもとに、加入希望者が将来保険金を請求する可能性(リスク)を判断します。もしリスクが高いと判断されれば、保険金を支払う機会も多くなるため、契約条件の変更や加入を断られることがあります。
そのため、告知内容によっては、
- 身体の特定部位だけを保障しない「部位不担保」となる
- 保険料が高くなる
- 保険金が削減される
- 保険に加入できない
といった対応が取られることがあります。
しかし、こうしたルールがあるからこそ保険の公平性が保たれ、保障が受けられるのです。
告知義務違反に該当するケース
告知書に記載していることがらについて、故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合
これらを行うと、「悪意重過失」としてペナルティが発生します。
悪意重過失とは、告知すべき重要な事項であることを知っていてわざと告知しなかったり、少し注意すれば告知すべき重要な事項であることがわかるのに告知しなかったりする場合をいいます。
故意の告知義務違反は絶対に行ってはいけませんが、故意でなくても違反になる場合もあります。
風邪などご自身にとってはささいなことがらであっても、医師の診察を受けた場合は告知が必要になることがあります。告知を行う際は自己判断せず、些細な事でも正確に伝えることが大切です。
また、告知すべきか判断がつかない場合は、保険会社が設けている告知専用のフリーダイヤル等に問い合わせてみるといいでしょう。
告知義務違反が疑われる場合、保険会社は病歴などを病院へ確認することがあります。
告知義務違反が発覚すると、保険会社からの契約解除や、保険金受け取り時に保険金が支払われないといったこともありえます。
このようなトラブルを防ぐためにも、間違いがないかどうか慎重に確認し告知をしましょう。
告知義務違反をするとどうなる?
告知義務違反が発覚した場合、保険会社は保険契約を結んだ時から2年間は契約を解除できます。
この制度を利用して「告知義務違反をして保険に加入しても、規定の年数が経つと解除されないから数年間発覚しなければ良い」と考える方もいます。
しかし、保険の責任開始期から2年以上が経っていたとしても、契約を解除される可能性はあります。
告知義務違反を理由に保険契約を解除されてしまうと、支払った保険料は原則返還されません。また、保障期間中に発生した事案の保険金も支払われることはありません。
不正確な告知をしてしまったら
もし加入後に不正確な告知内容があったと分かった場合は、「追加告知(告知訂正)」を行うことができます。
追加告知を行うことで契約継続の可能性が高まりますが、追加告知の内容によっては、契約解除となる場合や、数年間保障しない期間が設けられるなど、何らかの条件が付く可能性があります。
保険会社や商品によっては追加告知が認められない場合もありますので、早めに保険会社にご相談することが重要です。
また、仮に保険の営業担当者から虚偽の申告を勧められた場合は「不告知教唆」という法律違反行為にあたります。
このような行為を行う募集人は保険業法に違反しており、信頼できる担当者ではありません。そのような事実があったことを後で立証するのは非常に難しく、最終的に不利益を被るのは契約者自身となるため、不告知教唆をするような募集人からは加入しないよう注意が必要です。
正しくない告知はすべてを無駄にしてしまう大きなリスクを背負うことになりますので、ありのままを正確に告知しましょう。
まとめ
ここまで解説してきたとおり、保険契約の解除が行われると、既に支払った保険料は原則戻ってくることはありません。保障期間中に発生した保険金や給付金の支払いもありませんし、解約返戻金がある場合は返還されます。
正確な告知をしないことによる損失はとても大きいです。
せっかく契約した保険が無効になってしまわないよう、告知は慎重に行いましょう。

 0120-873-100
0120-873-100