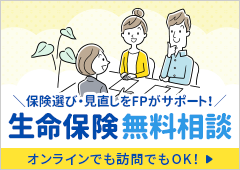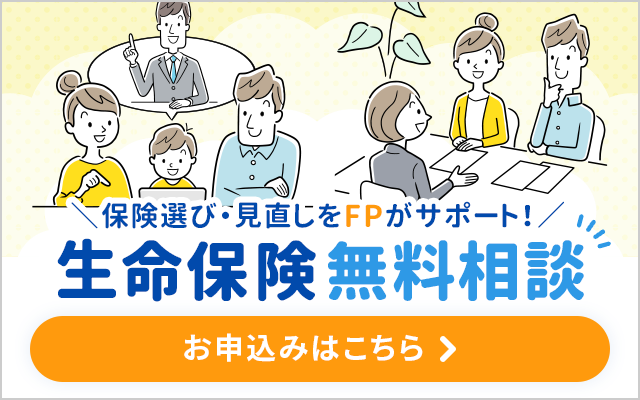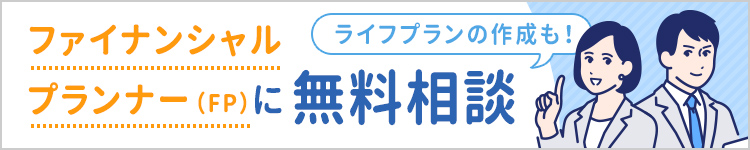老後資金のための資産運用とは?iDeCoとNISAを比較
更新日:
皆さんは老後に向けて何か対策をされていますか?
老後の備えを意識したとき、まず「老後資金はいくら必要になるのか」「公的年金でいくらもらえるのか」が気になるところです。
公的年金の現状をふまえると、ご自身でも老後資金の準備をしておく必要があります。
老後資金対策にはさまざまな貯蓄方法や資産形成商品がありますが、その中でも効率よく資産を増やせる手段として注目されているのが、「iDeCo」や「NISA」です。
この記事では、公的年金の現状を整理した上で、iDeCoとNISAの特徴やメリット・デメリットを解説し、最適な活用方法をご紹介します。
公的年金制度の現状
日本の公的年金制度は「国民皆年金」という形態になっており、20歳以上の方は全員国民年金に加入しています。
国民年金は、加入者を下記の3種類に分けています。
- 第1号被保険者:自営業、学生など
- 第2号被保険者:会社員、公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
この種類によって、将来受け取れる年金の金額は大きく変わります。
- 【国民年金(老齢基礎年金)】
第1号・3号被保険者 自営業、学生、第2号被保険者に扶養されている配偶者など - 【国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金】
第2号被保険者 会社員、公務員など
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めた場合、65歳から満額が支給されます。(保険料免除期間がある方は別途計算が必要になります。)
厚生年金は、会社員、公務員などの厚生年金保険に加入していた方に対し、給与や賞与の額に応じて支給されます。
公的年金だけでは足りない?
たとえば自営業の方が老齢基礎年金を満額受け取れる場合、1年間で831,696円、月額にすると約6.9万円(令和7年度時点)の支給があります。
しかし、老後に必要な最低日常生活費は夫婦で月に約23.2万円、ゆとりある生活には約37.9万円が必要とされています。
夫婦二人で老齢基礎年金を満額受け取れたとしても月額約13.8万円にとどまるため、ゆとりある生活を送るには約24.1万円が不足する計算になります。
近年、国民年金の受給額は物価や賃金の上昇に伴い増額しています。
ただその伸び率は、将来の給与水準を確保するために物価や賃金の伸びよりも低く抑えられ、実質的には目減りしている状況です。
支払う保険料も毎年度見直しが行われ段階的に引き上がっており、令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円、令和7年度は月額17,510円となっています。
保険料を支払う現役世代が減少しているため、今後も年金は実質的に目減りしていくことが予想されます。
老後の収入があるのは心強いものの、公的年金の支給額だけでは不安が残ります。
iDeCoとは
「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金(個人型DC)のことをいいます。
401kやDCという単語を聞いたことのある方も多いと思いますが、これらはすべて「確定拠出年金」のことを指しています。
かつては自営業者と勤務先に企業年金のない会社員しか加入できませんでしたが、2017年1月から規制が緩和されたことにより、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方と国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方は、ほぼ全員が加入できるようになりました(2027年1月より70歳未満まで拡大予定)。
iDeCoは任意で加入できる私的年金制度で、いわばご自身で老後の資金を作る制度です。
金融機関(運営管理機関)が用意している預金や投資信託、保険などの金融商品の中からご自身で選び、毎月掛け金を払い込みます。60歳以降に給付金を受け取ることができますが、投資なので受取金額は運用実績によって変わってきます。
iDeCoの口座開設は、保険会社や証券会社、銀行などから申し込むことができます。
商品は1つだけを選ぶことも、複数の商品を組み合わせて運用することも可能です。運用商品を途中で変更することもできますが、利用できるのは1つの金融機関に限られます。
金融機関はいつでも変更可能ですが、移管手続きには時間がかかったり、手数料が発生したりすることがあります。また、移管中は運用ができないので、金融機関は慎重に選ぶ必要があります。
iDeCoのメリット
iDeCo最大のメリットは、「支払い時・運用時・受け取り時」の3つの税制優遇です。
掛金全額が所得控除
毎月の掛金(支払ったお金)が全額所得控除されます。
運用益が非課税
金融商品を運用して利益が出たら、その分の所得は課税対象となり、税金を納めなくてはなりません。
しかし、iDeCoの運用益は全額非課税で再投資することができます。
受け取り時にも控除
<年金として受け取る場合>
「公的年金等控除」の対象となります。
60歳になったら、5年以上20年以下の期間で年金を受け取ることができます。受け取り開始時期は60歳から75歳までの間で選択できます。
<一時金として一括で受け取る場合>
「退職所得控除」の対象となります。
60歳になったら、75歳になるまでの期間に一括で年金を受け取ることができます。(60歳からiDeCoの年金を受け取るためには、iDeCoへの加入期間が10年以上必要になります。)
年金か一時金のどちらかではなく、半分を一時金として受け取り、残りの半分を年金として受け取る方法を取り扱っている金融機関もあります。
iDeCoのデメリット
受け取る金額が少なくなる可能性がある
金融商品なので投資のリスクはつきものです。
商品の運用が好調であれば受け取る年金が増える可能性がありますが、運用次第では支払い金額よりも受け取り金額が少なくなってしまう可能性もあります。
手数料が掛かる
iDeCoに加入する際の手数料や、毎月支払う口座管理料、投資信託を選ぶ場合には信託報酬などがかかります。手数料や金額は金融機関や商品によって異なるため、必ず確認しましょう。
長い期間付き合うことを考えると、金融機関選びはとても重要といえます。
60歳になるまで引き出せない
iDeCoで積み立てたお金を途中で引き出すことは原則できません。
自分のタイミングで引き出すことができないのはデメリットではありますが、貯蓄が苦手な方にとってはメリットでもあります。60歳までは引き出せないので、未来の自分へ確実にお金を渡すことができます。
お金があると使ってしまう方にはおすすめです。
NISAとは
「NISA(小額投資非課税制度)」とは、日本に住む18歳以上の方を対象とした、少額からの投資を行う個人のための税制優遇制度です。
通常、投資で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAではこの税金がかかりません。
2024年1月から始まった新NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの非課税投資枠があります。いずれも非課税保有期間が無期限となり、長期保有が可能になりました。
さらに「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用可能となり、投資の選択肢が広がったため、より積立投資がしやすくなりました。
NISAでは「つみたて投資枠」が年間120万円、「成長投資枠」が年間240万円、合計で年間360万円を非課税で投資することが可能です。
非課税保有限度額は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」合わせて1,800万円です。ただし、「つみたて投資枠」だけで1,800万円を活用することは可能ですが、「成長投資枠」の上限は最大1,200万円までとなっています。
投資対象商品として、「つみたて投資枠」には一定の条件を満たした投資信託、「成長投資枠」には上場株式や投資信託などがあります。ただし、対象外となる商品があるため注意が必要です(整理・監理銘柄、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託など)。
NISAのメリット
投資で得られた運用益・配当金・分配金は一生涯非課税
通常、投資で得られた利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAでは生涯投資枠の上限1,800万円までの投資で得られた利益に対し、一生涯税金がかかりません。
仮に投資した1,800万円が資産額2,800万円になったとして、それを売却し1,000万円の運用益を得た場合、通常は約203万円の税金が引かれてしまいますが、NISAなら税金がかかりません。
また、投資した1,800万円が資産額2,800万円になり、2%の配当金(分配金)が得られた場合でも、毎年56万円を非課税で受け取ることができます。
少額でも投資を始められる
NISAは少額から始められます。
例えば、ネット証券のSBI証券・楽天証券・マネックス証券などでは、投資信託であれば100円から始められます。少額での投資の場合、増えるスピードは遅いのですが、今まで投資をしたことがない方にも始めやすい設計になっています。
いつでも売却可能で、翌年枠が復活
NISAはいつでも売却して引き出すことができます。そのため、老後資金や教育資金など、さまざまな用途でお金を貯めることに適しています。
さらに売却枠の再利用も可能で、売却した翌年に「投資元本ベース」で非課税投資枠が復活します。
例えば、生涯投資枠の上限1,800万円投資し、そのうち200万円を売却したとすると、売却して空いた分の枠200万円分は翌年から利用することができます。
NISAのデメリット
短期で引き出す予定のお金の運用には向かない
NISAで購入できる商品は、投資信託、ETF、株式などです。
NISAに限ったことではありませんが、投資信託や株は値動きがあり、元本割れの可能性があります。日々の生活のために必要なお金や、短い期間で訪れるようなライフイベントのために貯めているのに、元本割れしてしまっては大変です。
あくまで過去データの分析結果ですが、『ウォール街のランダム・ウォーカー』(バートン・マルキール著)には、長期投資を15年以上続けることで、元本割れの可能性をゼロに近づけることができると書かれています。
また金融庁の『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』にも、1989年以降、5年という短い積立投資期間では元本割れになることがあったものの、20年という長い期間では元本割れとなったケースは無かったと書かれています。
これらの分析結果がすべてではありませんが、NISAは「長期・積立・分散」で投資を行うことで、良い運用成果が出やすいといえます。10年以上先に使うであろうお金(老後資金や教育資金など)を貯めるために活用しましょう。
「損益通算」や「繰越控除」ができない
「損益通算」は、複数の口座で生まれた利益と損失を合算する仕組みです。また「繰越控除」は、損益通算しても損失があるときに、最大3年間その損失を繰り越して翌年の利益から差引くことができる仕組みです。
どちらも投資の利益にかかる税金の負担を減らすのに役立ちますが、NISAは「損益通算」や「繰越控除」の対象外となっています。
海外に引っ越すとNISA口座を継続できない金融機関が多い
NISAを利用できるのは「日本に住む、1月1日時点で18歳以上の人」です。ところが、海外転勤・赴任すると「非居住者」となり、NISAを利用できなくなってしまいます。
救済措置として、「最長5年の海外転勤等」であれば、NISA口座で保有してきた資産を保有することができます。しかし、この制度に対応している金融機関は少ないのが現状です。
なお、海外転勤・赴任しているのに手続きをせずにいることが発覚すると、NISA口座・課税口座が全て廃止され、資産の強制売却(現金化)となります。
iDeCoとNISAを比較
| iDeCo | NISA | ||
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
| 対象年齢 |
原則20歳 ※2027年1月より70歳未満まで拡大予定 |
18歳以上 | |
| 年間投資上限額 |
年間24.0万円 ※2027年1月より年間27.6万円~90.0万円に引き上げ予定 |
120万円 | 240万円 |
| 総額1,800万円 (成長投資枠 1,200万円) |
|||
| 税制優遇 |
受取時も優遇あり |
運用益が非課税 | |
| 投資対象 |
|
長期投資に適した投資信託 |
|
| 引き出し | 原則60歳以降 | いつでも可能 | |
老後資産をつくるにあたり、iDeCoもNISAも長期的に資産を運用し、税制優遇があることなどが共通点として挙げられます。
iDeCoは私的年金制度のため、60歳になるまではお金を引き出すことができません。
しかし「老後資産の構築」という点で考えると、デメリットばかりではありません。ご自身から資産を守る目的で検討されるのも一つの手ではないでしょうか。
また、「支払い時・運用時・受け取り時」に3つの税制優遇を受けられるのも大きなメリットです。
NISAは自由にお金を引き出すことができますので、万一の急な出費にも対応しやすいです。
また、利益が非課税であることに加え、投資信託や株式などの商品を通じてご自身のリスク許容度に応じた運用が可能なため、リターンを最大化したい方に向いています。
少額でも投資を始められるので、今まで投資をしたことがない方にもおすすめです。
iDeCoが向いている人
- 元本確保型商品(定期預金など)を選択することで、できるだけリスクを抑えて老後資金を準備したい
- 毎年の所得税や住民税の税負担を軽減したい
- 貯金をするのが苦手
NISAが向いている人
- 老後以外の目的でも資金を使う可能性がある
- 比較的短期的な資産成長を望み、投資額を柔軟に調整したい
- 少額から投資を始めてみたい
iDeCoとNISAは併用することができますので、どちらも活用することを検討してみるのもいいかもしれません。
併用がおすすめの人
- 資金に十分な余裕がある
- 老後資金の確実な準備と投資の柔軟性、両方を求めたい
まとめ
資金の目的と必要になるタイミングによって選び方は変わってきます。
公的年金だけでは老後資金が不足する現状をふまえると、自助努力による資産形成はとても重要です。
国の政策により、ご自身の判断で老後資金の準備をするための方法や商品は増えてきています。ご自身に合った資産形成の方法を選びましょう。
老後資金についてお悩みの方、自分に合った資産形成の方法を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
保険のプロがご相談にお応えします

 0120-873-100
0120-873-100