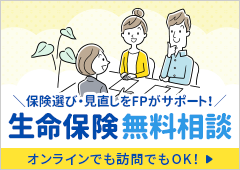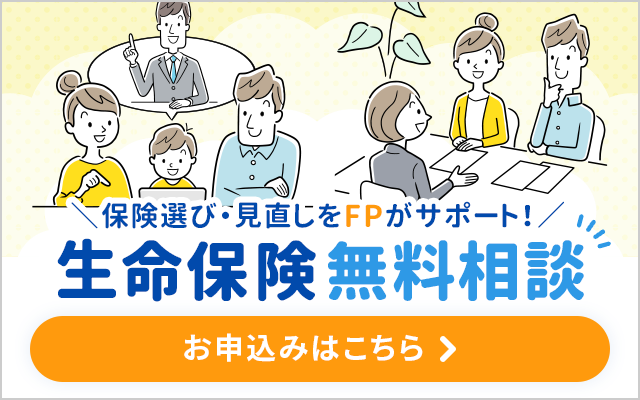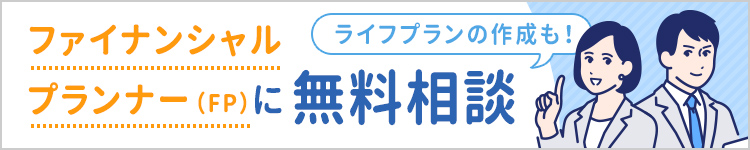老後資金の必要額とは?
公的年金から考えるシミュレーション方法
更新日:
楽しく穏やかな老後を過ごすために、老後資金は欠かせません。
公的な年金だけでは不足してしまうことは分かっていても、「果たして自分がどれくらいの余裕資金を準備すれば良いのか」という具体的な金額はぼんやりとしている方も多いと思います。
各媒体では「老後資金として3,000万円は必要」「1億円あれば困らない」などと、さまざまな意見が飛び交っていますが、本当にそれほど多額の老後資金を必要とするのでしょうか。
この記事では、老後資金が3,000万円必要と言われている根拠や、ご自身に必要な老後資金をざっくりとシミュレーションするための計算方法などを解説していきます。
老後資金とは?
老後資金とは、一般的に「退職してから亡くなるまでの生活をまかなうための資金」を指します。
収入が減少してから亡くなるまでの期間、余裕を持って過ごしたいですよね。
老後は公的年金が収入のメインになる方が多いと思いますが、給付される年金だけで足りるのかと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
基本的な考え方として、老後資金は以下の計算式で必要額を算出します。
老後の生活費+その他の出費-老後の収入(公的年金など)=老後資金
そのうちの主な支出としては以下のものが挙げられます。
- 家賃・光熱費などの費用や、食費・日用品などの生活費
- 医療費や住居・車の維持費
- 趣味や旅行といった娯楽費、冠婚葬祭などの費用
老後の金銭的な心配をすることなく、円滑に老後生活が送れるようにするためには、これらにかかる費用を事前に準備することが必要です。
しかし、実際に計算してみようとすると、①は持ち家または賃貸のどちらに住んでいるかによって金額は異なります。②や③もそれぞれの環境や、求める娯楽の範囲で金額は大きく変わってきます。
また、亡くなるまでの期間によっても必要額は変わります。長く生きれば生きるほど必要な老後資金が多くなること、これを長生きリスクと呼びます。
老後の生活に備えるには、このようなリスクも把握しておかなくてはいけません。
それでは、一般的に言われている「老後資金=3,000万円」とは、どのような内訳による目安となっているのでしょうか。
「老後資金のモデルケース=3,000万円」の内訳
一般的に言われる3,000万円という数字は、「現役時代に会社員だった夫婦2人世帯」をモデルケースとして、
- ゆとりある老後生活費:約38万円
- 平均の公的年金月額:約23万円
- 65歳の定年後から活動的な70歳または75歳までの期間
という条件のもとで必要額をざっくりと計算し、予備費も含めたものとして広く知られている数字です。
ただし、この数字はあくまで上記の条件を前提としたモデルケースの場合の目安であり、すべての人に当てはまるものではありません。
前述のとおり、老後資金の必要額は、住居環境やライフスタイル、家族構成によって大きく異なります。
また、社会情勢の変化を考慮しておくことも大切です。
平均寿命が延びていることを考えると、活動的な期間はもう少し長くみておいたほうが安心かもしれません。
生活費に大きく影響する物価の上昇や、年齢とともに増えやすい医療費・介護費用の突発的な出費も見込んでおくと良いでしょう。
公的年金制度のしくみ
必要な老後資金を検討するために、まずはご自身がどのくらいの年金を受け取ることができるのか把握しましょう。
「1階建て」「2階建て」という言葉を聞いたことはありますか?
日本の公的年金制度は「国民皆年金」制度となっており、20歳以上の国民は皆国民年金に加入しています。
自営業者などの第1号被保険者は国民年金のみですが、会社員などは第2号被保険者と呼ばれ、国民年金と厚生年金に加入しています。
このような加入する年金の種類の違いが、いわゆる1階建て、2階建てと呼ばれているのです。
加入している年金の種類が異なるため、もちろん受け取れる年金の額にも違いが出てきます。
必要な老後資金のシミュレーション方法
それでは、実際に老後資金をシミュレーションするために、目安となる支出や収入の平均額、平均余命を見ていきます。
老後の支出額
生命保険文化センターが行った調査によると、夫婦2人が老後生活を送るうえで必要と考える『最低日常生活費』は、月額で約23.2万円です。
| 世帯 | 支出金額 |
|---|---|
| 夫婦世帯 | 最低日常生活費 23.2万円/月 |
| 単身世帯 | 最低日常生活費 11.6万円/月 (夫婦世帯23.2万円から仮定) |
一方、『最低日常生活費』以外にゆとりある老後生活を送るための費用として必要と考える金額は、月額で約14.8万円でした。
つまり、ゆとりある老後生活を送るには『最低日常生活費』と『ゆとりのための上乗せ額』を合計した、約37.9万円が必要ということになります。
| 世帯 | 支出金額 |
|---|---|
| 夫婦世帯 | ゆとりある老後生活費 37.9万円/月 |
| 単身世帯 | ゆとりある老後生活費 19万円/月 (夫婦世帯37.9万円から仮定) |
老後の収入額
公的年金の平均受給額は、厚生年金加入者は男性では年額約200万円、女性では約128万円程度の方が多いとされています(基礎年金と厚生年金の合計額)。
月額にすると男性は16.6万円、女性は10.7万円となり、夫婦合わせて約27.3万円支給される計算になります。
一方、自営業者などの国民年金のみ加入されていて、満額で受け取ることができる方は、年額831,696円(令和7年度時点)の支給があります。
夫婦二人で国民基礎年金を満額受け取れる場合は、年額約166万円、月額にすると夫婦二人で約13.8万円となります。
上記の金額はあくまでも全体としての平均額ですので、加入している年金の種類や年数、単身なのか夫婦二人なのかによって目安金額は異なってきます。
以下の表では、一例として世帯別の受給金額を計算していますので、目安としてご覧ください。
世帯パターン別 老齢年金受給額(2025年度(令和7年度))
夫婦2人世帯(夫:会社員、妻:専業主婦)
夫のみ厚生年金加入、妻は国民年金(専業主婦)
| 夫年収 500万円 | 夫年収 600万円 |
|---|---|
| 229,966円 (老齢基礎年金2人分+老齢厚生年金) |
248,236円 (老齢基礎年金2人分+老齢厚生年金) |
夫婦2人世帯(夫婦とも会社員)
夫婦ともに厚生年金加入(共働き世帯)
| 夫年収500万円・妻年収300万円 | 夫年収600万円・妻年収350万円 |
|---|---|
| 284,776円 (老齢基礎年金2人分+老齢厚生年金2人分) |
312,181円 (老齢基礎年金2人分+老齢厚生年金2人分) |
単身世帯(会社員)
厚生年金加入の単身者
| 年収 300万円 | 年収 500万円 |
|---|---|
| 124,118円 (老齢基礎年金+老齢厚生年金) |
160,658円 (老齢基礎年金+老齢厚生年金) |
夫婦2人世帯(自営業)
夫婦ともに国民年金のみ加入
| 夫年収500万円・妻年収300万円 | 夫年収600万円・妻年収350万円 |
|---|---|
| 138,616円 (老齢基礎年金2人分のみ) |
138,616円 (老齢基礎年金2人分のみ) |
- 2025年度(令和7年度)の年金額に基づいて計算しています。年金額は毎年4月に改定されます。
- 加入期間40年で統一して計算しています。実際の受給額は個人の加入履歴により異なります。
- 平均標準報酬月額は年収を12で割った概算値を使用しています。賞与の割合により実際の金額は変動します。
- 厚生年金の受給には1年以上の加入期間、老齢基礎年金の受給には10年以上の保険料納付済期間が必要です。
- 在職老齢年金制度により、65歳以降も働く場合は年金の一部が支給停止される場合があります。
- 物価・賃金の変動により、将来の年金額は変更される可能性があります。
- 詳細な年金見込額は日本年金機構の「ねんきんネット」でご確認ください。
平均余命
厚生労働省が公表している「令和4年簡易生命表」によると、65歳時の平均余命は男性が19.44年、女性が24.30年です。
つまり、男性は65歳から約20年、女性は約24年生きるということになります。
世帯別の老後資金をシミュレーション
以上のデータを元に、世帯別の老後資金の必要額を算出してみました。
夫婦2人世帯(夫:会社員、妻:専業主婦)の例
夫年収 500万円の場合
<最低日常生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 23.2万円×12ヵ月×29年間 =8,073.6万円 |
22.9万円×12ヵ月×24年間 =6,595.2万円 |
8,073.6万円-6,595.2万円 =1,478.4万円 |
<ゆとりある老後生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 37.9万円×12ヵ月×29年間 =13,189.2万円 |
22.9万円×12ヵ月×24年間 =6,595.2万円 |
13,189.2万円-6,595.2万円 =6,594万円 |
夫婦2人世帯(夫婦とも会社員)の例
夫年収500万円・妻年収300万円の場合
<最低日常生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 23.2万円×12ヵ月×29年間 =8,073.6万円 |
28.4万円×12ヵ月×24年間 =8,179.2円 |
8,073.6万円-8,179.2円 =-105.6万円(余剰) |
<ゆとりある老後生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 37.9万円×12ヵ月×29年間 =13,189.2万円 |
28.4万円×12ヵ月×24年間 =8,179.2円 |
13,189.2万円-8,179.2円 =5,010万円 |
単身世帯(会社員)の例
年収 300万円の場合
<最低日常生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 11.6万円×12ヵ月×29年間 =4,036.8万円 |
12.4万円×12ヵ月×24年間 =3,571.2万円 |
4,036.8万円-3,571.2万円 =465.6万円 |
<ゆとりある老後生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 19.0万円×12ヵ月×29年間 =5,472万円 |
12.4万円×12ヵ月×24年間 =3,571.2万円 |
5,472万円-3,571.2万円 =1,900.8万円 |
夫婦2人世帯(自営業)の例
夫年収500万円・妻年収300万円の場合
<最低日常生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 23.2万円×12ヵ月×29年間 =8,073.6万円 |
13.8万円×12ヵ月×24年間 =3,974.4万円 |
8,073.6万円-3,974.4万円 =4,099.2万円 |
<ゆとりある老後生活費での試算>
| 支出 | 収入 | 必要な老後資金 |
|---|---|---|
| 37.9万円×12ヵ月×29年間 =13,189.2万円 |
13.8万円×12ヵ月×24年間 =3,974.4万円 |
13,200.8万円-4,003.2万円 =9,214.8万円 |
この試算は60歳から89歳までの29年間の支出と、65歳から89歳までの24年間の年金収入を前提としています。
これらの一例はあくまで目安ですが、計算式にあてはめた結果を見ると、自営業世帯すなわち老齢基礎年金(国民年金)のみを受け取る場合、用意しなくてはならない老後資金が最も大きいことが分かります。
自助努力による老後資金の補てんが必須であるということです。
また、平均寿命以上に長生きした場合には、さらに老後資金が必要となります。
老後の衣食住の確保や、安心して医療機関を受診できる環境も合わせて確保しておきたいものです。
なお、計算には負債(住宅ローンなど)や一時所得(退職金など)は含まれていません。ご自身の背景を加味しながら、それぞれに適した必要な老後資金を算出してみてください。
まとめ
公的年金だけで、老後に必要なお金をまかなうことはできません。
老齢基礎年金(国民年金)の受給額は毎年見直しがされているため、この先受給できる金額が減ってしまう可能性があり、国からも自助努力を呼びかけられています。
老後にしっかりとお金を残すためには、早めの資産形成が大切です。
新NISAや確定拠出年金(iDeCo)、個人年金保険などを利用して、ご自身で老後の準備を進めていきましょう。

 0120-873-100
0120-873-100